~ 支援機関との連携による医療機関での障害者雇用の推進 ~
- 事業所名
- 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会中津医療福祉センター
- 所在地
- 大阪府大阪市
- 事業内容
- 総合病院および関連福祉・介護諸施設
- 従業員数
- 1,800名(平成26(2014)年6月現在)
- うち障害者数
- 22名(うち、重度6名)
障害 人数 従事業務 視覚障害 4 リハビリ、清掃、事務 聴覚・言語障害 2 事務 肢体不自由 7 医師、調理、介護、介護助手、事務 内部障害 2 事務 知的障害 6 介護助手、清掃 精神障害 1 介護助手 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次
 大阪府済生会 中津病院 |
1. はじめに、事業所の概要
(1)はじめに
医療業には除外率が設定されていることからも分かるように、病院での障害者雇用は今まで「難しい領域」と考えられてきた。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページの「障害者雇用リファレンスサービス」に掲載されている2,000件超の事例のうち医療関係事例はわずか4%に過ぎない。そこで、今回は病院における障害者雇用の状況を知るために、社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会中津医療福祉センター(以下「中津センター」という。)を訪問し、筑井企画部長、田中人事課長をはじめ、中津センターの中核となる中津病院の奥井看護副部長、看護助手の後さん、さらに、就労支援機関として「大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合」(通称「エル・チャレンジ」、以下、通称で記述する。)の上国料就労支援課長、「社会福祉法人加島友愛会」の太田ジョブコーチにも同席していただき、障害者雇用についてのお話を伺った。
(2)事業所の概要
中津センターは、大正5(1916)年に開院し、平成28(2016)年には創立100周年を迎える中津病院を中核に8施設を運営するセンターである。
中津病院は、(ア)新たな価値の創造、(イ)患者さん第一、(ウ)人間尊重と効率運営という3つの理念を掲げ、JR大阪駅、市営地下鉄、阪急・阪神各私鉄梅田駅より徒歩10分以内という好立地条件のもと、1日約1,300名の外来患者を受け入れ、31の診療科と748床を有する大阪屈指の総合医療機関で、地域の他の医療機関、施設との連携を一層深め、地域一体となった切れ目のない医療を提供し、地域住民の方々に信頼されている。
中津センターでは、職員・医師1,800名のうち22名の障害者が働いている。従事業務は多岐にわたっているが、主に身体障害者は事務系、知的障害者はベッドメイキングや清掃などが中心となっている。
障害者雇用の内訳
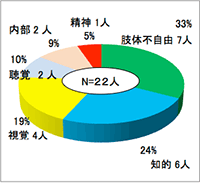
障害種別
|
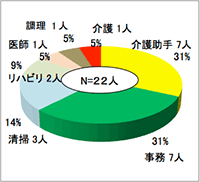
従事業務
|
2. 障害者雇用の契機、知的障害者の雇用について
(1)障害者雇用の契機
現在でこそ22名もの障害者を雇用している中津センターであるが、以前は法定雇用率も未達成で、中津センターにおける障害者雇用納付金の額は年間約600万円になっていたこともあった。しかし、元来から「施薬救療」の精神のもと、無料低額診療事業に力を入れるなど、社会的弱者に対するサポートを使命としていたセンターの意義から、障害者雇用に対しても企業の社会的責任(コンプライアンス)を果たすべく、平成23(2011)年度より障害者雇用への取組が本格的に開始された。
「当初は、事務職として身体障害者を雇用していたのですが、それだけでは障害者雇用が満たされないと感じていた中で、エル・チャレンジさんとの出会いが病院のその後の障害者雇用を大きく進展させることとなりました」と中津センター企画部長の筑井さんは語る。エル・チャレンジは知的障害者を中心に就労に向け、ビルメンテナンス・清掃作業等を訓練する支援機関である。
エル・チャレンジを中心とした障害者雇用に関する相談の中、社会福祉法人加島友愛会、大阪障害者職業センターを含む支援機関がオブザーバーとして参加する、中津センターの「障害者職場定着推進チーム」の発足につながっていくことになる。
(2)知的障害者の雇用について
とはいえ、知的障害者を病院で雇用することに不安はなかったのだろうか、その疑問を率直に筑井さんに聞いてみた。
「不安がなかったとは言えませんが、他の病院でも成功している事例を聞いていましたので、まずは一歩を進めることができました」と、実は、同じ大阪府済生会の他の医療福祉センターの吹田病院や千里病院では以前からエル・チャレンジで訓練を受けた知的障害者を清掃等で雇用し、定着しているという実績があった。また、各医療福祉センターでは、もともと人権研修に関する勉強会も盛んに行われていた。これらの基盤が、中津センターでの知的障害者の受入れに安心感を与えていた。他のセンターでの状況を確認ができるという横のつながりは、グループ企業としての強みとも言える。
さらに、筑井さんは「エル・チャレンジさんや加島友愛会さんが障害者受入れの前段階から丁寧に相談に乗ってくださったことも、現場の方々への安心感につながりました」と振り返る。
一方、エル・チャレンジの就労支援課長上国料さんは「いくらグループ内の病院で障害者雇用の経験があるとはいえ、中津センターでは初めての受入れになるわけで、その点は他の病院は関係なく、一緒に作業をする現場の方は苦労されたと思います」と言う。
上国料さんが言うように、いくら人事や雇用管理部門が障害者雇用を進めようとしても、現場の受入れ体制や安心感が得られなければ、事はうまく進まないのが現実である。受入れの前にジョブコーチを中心にどのような作業であれば受入れが可能なのか、といった作業工程の検討や見直しが進められた。また、併せて障害の特性についての勉強も行われた。
そもそも、中津センターでは、看護助手が他の業務とともにベッドメイキングや清掃なども行っており、その中からどの作業なら知的障害者に対応可能であるのかという作業の切り出しからジョブコーチとともに始められた。そして、作業時間の流れや障害者の担当箇所など細部にわたり、綿密な打合せが行われ、時にはジョブコーチが1日の作業を実践し、見直し、改善することも少なくなかった。作業工程が決定すると、それに対応可能な障害者を選定し、実習の形から受入れが進められた。
今回、障害者雇用がうまくいくポイントは何かと聞くと、中津センターの方々が口をそろえて「雇用前にじっくり時間をかけて準備をすること」との答えであったが、まさに、それを物語る丁寧さである。もちろん、障害者の受入れ後もジョブコーチが一定期間付き添い、作業工程を都度見直しながら、雇用の定着へとつなげていった。
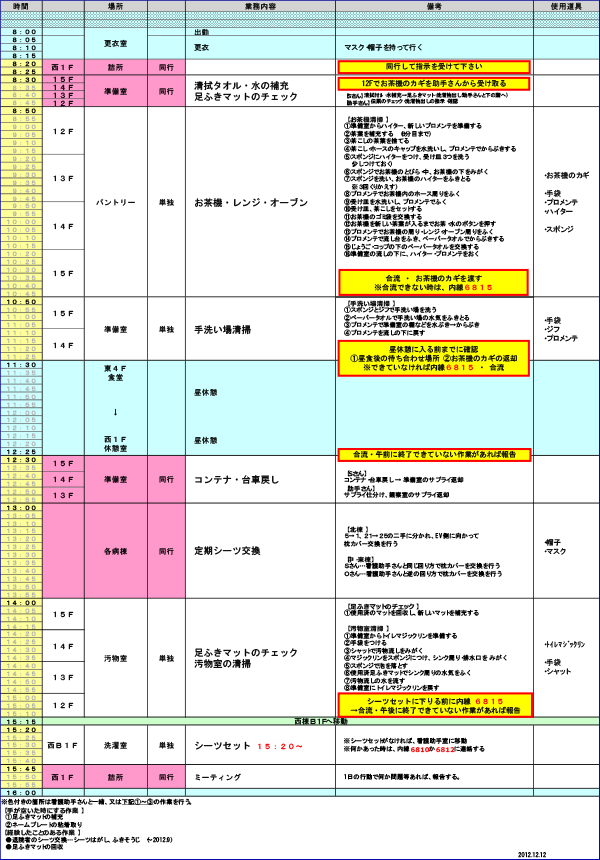
作業工程票
|
3. 現場の理解
現場で一緒に働く看護助手の後さんは、「私たちは、障害者のことが全く分からない状態ですから、事前にお話していただいた障害者の特性や個性等、対応が分からない時にジョブコーチさんに聞くとすぐにアドバイスをしてくださるといった安心感がありがたかったです」と言う。
反面、上国料さんは「現場の方々は、年齢的にもお母さんのような存在で、優しく見守ってくださり、障害を理解しようとし、現に理解してくださっています。とてもありがたいです」と、現場の方の理解がなければ成り立たないと述べる。
例えば、看護副部長の奥井さんは自閉症を併せもつ方が職員用のエレベーターに乗る際に、我先にと乗り込む様子をみて、ジョブコーチに相談したという。そして、「ジョブコーチさんから障害特性の説明を聞いて、その人の特性なんだなと納得し、現場の他の人たちにも伝えました」と、笑顔で雇用当初のことを振り返ってくださった。このような行為を見かけた時に、普通であれば、ジョブコーチに愚痴を言うことはあるにせよ、相談をするだろうか。この行為について、「悪気があってしているわけではなく、障害からきているのかもしれない」と考えたり、「注意をするのであればどのように言えばよいのだろうか」と本人に向き合おうとしたり、ジョブコーチから得られた情報を現場で共有したり・・・。インタビューの中で、現場の方々が協力して、障害者と向き合い、理解しようとする姿勢がひしひしと感じられた。
控室にも伺い休憩の様子を見させていただいたが、現場での緊張感とはうって変わってアットホームな雰囲気が伝わってきた。現場の方々は障害のある方たちについて「十分戦力になっていて、欠かせない存在」と笑顔で話し、障害者たちは「仕事は楽しいです」と答えてくださった。
決してお世辞でも遠慮でもなく、管理職、現場、支援者がお互いを尊重しながら、障害者雇用という1つの目標に対し役割を明確にし、良好な関係で障害者雇用が進められたことがインタビューの雰囲気からも終始感じられた。このように明確な目標設定と絆こそが、22名もの障害者を雇用し、定着率向上につながる秘訣であり、企業の強さなのではないだろうか。
 ベットメイキングを行なっている Aさん ペアの看護師さんとの息もピッタリ |
4. 今後について
現在、職場定着推進チームを発足させ、支援機関もオブザーバーとして参加し、勤務している障害者の勤務状況・健康状態等を定期的に確認し、フォローアップ体制を充実させている。
中津センター企画部長の筑井さんに今後の障害者雇用に関する展望を聞いてみた。
「当法人の雇用率は平成26(2014)年6月には2.3%までアップしましたが、今後、精神障害者が雇用率に算入されることにより、さらに多くの障害者雇用が求められてきます。コンプライアンスを果たすべく、法定雇用率を維持していくことが当面の目標になると思います。病院での障害者雇用の難しさは、病院という性質がもつ2面性にあると思います。一つは医療従事者としてどの患者さんに対しても分け隔てなく対応していこうという面。そして、もう一つは患者さんへのサービスについて障害のある方がどこまで貢献できるか冷静に判断する面。この両面のバランスを保ちながら、事業を進めていくことが重要と考えています。」
常に冷静沈着に状況を判断し、社会貢献を進める姿勢に、障害者雇用のヒントがあるのかもしれない。常に良質な医療および福祉を、安全に提供し、かつ安心して利用し続けてもらえることを願っている現場において、医療機関での障害者雇用は、理解を得ることが困難な事例が多い中、管理者と現場・支援者がお互いの役割を認識しながら補完していくことがもう一つのポイントではないだろうか。
| 執筆者: | 関西学院大学人間福祉学部 講師 平 英司 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











