研修で学んだ職務創出に注力したことで、職場の生産性も向上した事例
- 事業所名
- 株式会社トリケミカル研究所(法人番号 2090001008148)
- 所在地
- 山梨県上野原市
- 事業内容
- 半導体・光ファイバーなどに使用する高純度化学材料の研究・開発・製造・販売
- 従業員数
- 121名
- うち障害者数
- 2名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 1 製造補助業務 内部障害 知的障害 重度1 製造補助業務 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - ■本事例の対象となる障害
- 知的障害
- 目次
-

事業所外観
1.事業所概要
(1)化学業界における位置づけ
化学工業分野における日本企業の年間出荷額は、プラスチック・ゴム製造等を加えた広い定義で考えると39兆円にものぼり(プラスチック・ゴムを除いても25兆円製造業の根幹を支える産業の一つといえる。
このような化学工業分野で、株式会社トリケミカル研究所は世界の化学薬品製造メーカーの中でも最高レベルの純度(99.9999%up)を誇る高付加価値化学薬品“ウルトラファインケミカル”を開発・製造・販売している企業であり、それらは主として半導体・光ファイバー・太陽電池といった最先端デバイス等の製造用材料として用いられている。
(2)半導体業界における役割
株式会社トリケミカル研究所の売上高の約6割は半導体製造用の化学薬品等である。半導体は、その宿命として継続的な微細化(=高集積化)が求められている。現在最先端の半導体の配線の幅は20nmから30nmと言われているが、研究レベルでは既に18nmや12nmといったところまでの検討が始まっている。ちなみに1nmとは1mmの百万分の一(0.000001mm)で、一般的な髪の毛の太さが0.07mm位と言われており、最先端半導体向けの材料には、わずかな不純物の混入も許されない。
また、半導体を製造するには、数百から千種類を超える化学薬品を使用するが、膨大な量を使用するものから、年間数グラムから数十キログラムしか使わないものまで様々ある。
株式会社トリケミカル研究所では"“ウルトラファインケミカル”を年間数百種類(累計では2000種類以上)、数ミリグラムから数十トンの幅広い単位のオーダーで、半導体製造メーカーのニーズに合わせて出荷している。
(3)経営に対する考え方等
株式会社トリケミカル研究所は、厳重な管理を要する化学薬品の製造を事業内容としていることから、創業から一貫して自然環境を守るための努力を続けてきた。現在では品質マネジメントシステムの国際標準規格ISO9001に加えて、環境マネジメントシステムの国際標準規格ISO14001の認証を取得しており、更なる環境保全活動に努めている。
また、コンプライアンス(法令遵守)及びリスク管理体制の整備を行い、法令のみならず定款、各種社内規程及び企業倫理の遵守にも努めている。
今後は、顧客をはじめ取引先や従業員、株主など全てのステークホルダー(利害関係者)の満足度向上を目指し、これまで以上にCSR(企業の社会的責任)に配慮した経営を進めていくこととしている。
(4)組織構成
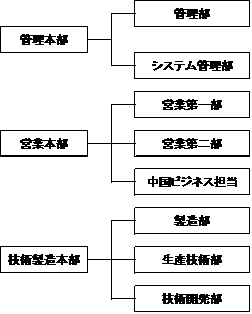
大きくは管理本部、営業本部、技術製造本部に分かれ、さらに、管理部、システム管理部、営業第一部、営業第二部、中国ビジネス担当、製造部、生産技術部、技術開発部、品質管理部などで構成されている。
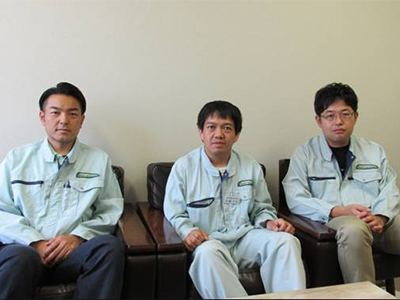
お話を伺った管理本部管理部総務課グループリーダー大野さん(左)
障害者の直属の上司である技術製造本部製造部製造一課課長佐藤さん(中央)
管理本部管理部総務課グループリーダー松井さん(右)(5)障害者雇用の理念
顧客をはじめとした全てのステークホルダーの満足度向上を目指し、、これまで以上にCSRに配慮した経営を進めていく中で、その取組の自然な流れとして障害者雇用にも取り組んでおり、企業の社会貢献や地域貢献の一環となっている。
2.取組の経緯、背景、きっかけ
法令遵守として、法定達成のための取組が直接のきっかけではあるが、上記の障害者雇用の理念にあるとおり、社会貢献や地域貢献の取組としても促進している。
15年程前に知的障害者を雇用したことが、障害者雇用の第一号である。その時の社員は5年程在籍して退職したが、良くも悪くもこの時の経験が、現在の障害者雇用に生かされている。
当時は障害者雇用が初めてであったこともあり、対応について右も左もわからず全くの手探りの状態で、支援機関を利用することもなく試行錯誤の連続で終わってしまった。当時の最大の反省点は、対応の甘さもあり、仕事の任せ方などが分からず、障害のある社員にとっても事業所にとっても不本意な結果となってしまったことである。
その後、10年程度の障害者雇用のブランクを経て、今回二人目となる知的障害のある人を新規に採用したものである。
3.取組の具体的な内容
株式会社トリケミカル研究所には障害のある社員が二名いるが、今回取り上げるのは、知的障害のある社員に関しての内容であり、以下、全て同様である。
(1)労働条件等
障害のない社員と労働条件の違いはない
ア 期間:期間の定めなし
イ 場所:工場内
ウ 時間:フルタイム。
エ 賃金:自社の賃金制度に基づく(2)仕事の内容
障害のない社員と同じであり、主に製造補助業務を担当している。

出荷準備のための説明書挿入・封かん作業の様子

出荷準備のためのビニールパック作業の様子

出荷準備のためのラベルはがし作業の様子

出荷準備のための塗装作業の様子
(3)助成金等の活用
ハローワークを通じた就労移行支援施設からの採用であったためそれに係る支援を受け、助成金に関しては障害者トライアル雇用奨励金などを活用した。
(4)労務管理上の工夫
ア 採用準備
失敗は許されないという思いから、まずは情報入手ということで、障害者職業センターが開催した就業支援基礎研修や事業主支援ワークショップなどに参加した。
その結果、障害者雇用のノウハウの基本を勉強することができた。特に、モデル事業所見学は実際の現場や担当者の話を聞くことができ、非常に参考となり、不安を解消することにつながった。これらの研修等参加による最大の収穫は、初めての障害者雇用で一番の課題であった、適切な仕事の割り振り方を学べたことである。
障害者雇用は、障害のある社員にどんな仕事を任せるかが最大のポイントであるため、研修で学んだとおり、職務を創り出すことに注力した。職務創出は職務の切り出しが前提であるため、結果としてこれらの作業は障害のない社員にとっても、本来の職務に専念できる環境を整備することにつながり、職場全体として生産性の向上というメリットを生んだ。
職務創出の流れは次のとおりである。
- (ア)
- 事業所内の仕事を再確認
作業工程・納期、身体負担・安全などを基準に、全ての事業所内の仕事の内容を再確認した。 - (イ)
- 職務の切り出し及び再構築
各従業員の作業のうち、作業順序の決まった平易な作業について、これを切り出し、集約した。新しい職務として再構築することで、障害のある社員の作業を数十種類作りだすことができた。
イ 採用
扱っている製品や作業内容の特質から、職場体験は困難であるという判断もあり、特別支援学校等ではなく、ハローワークを通じた就労移行支援施設からの採用となった。結果として、手厚い支援を受けることができたことも大きかった。特に、ジョブコーチが定期的にフォローしてくれたので、安心して取り組むことができた。
ウ 就労開始
創出した数十種類の仕事について、1~2か月の間に試しながら、作業の向き不向きや、できること・できないことを見極めることにより、多様な職務を受け持ってもらえることが可能となった。
エ 仕事の指示・OJT
毎日全く同じ作業ということはなく、随時、仕事内容をエクセルにまとめて表示している。具体的には、当日の作業に関し、優先度を必ず明示するように工夫している。優先度が明示されていない場合、判断するに当たって混乱してしまうからである。
また、作業内容は、一度創り出せば変わらないというものではなく、製品の仕様変更等により細かい部分が変化するため、随時、OJTを通じて習得してもらっている。その際、覚えられるまで指導担当者が付くことになるが、長期的に見れば、新規職務の創出は生産性の向上につながっている。
なお、社員としての心構えや言葉遣いやコミュニケーションについても、適宜、丁寧に指導している。
オ エピソード等
知的障害のあるSさんとその上司に話を伺うことができたので、以下に紹介する。
- (ア)
- Sさんへのインタビュー
-入社のきっかけは?
「就労移行支援事業所にいたとき、求人を見て応募しました。」
-就職してどうですか?
「やってみてよかったです。」
-仕事は楽しいですか?
「やり方を教えてもらって、いろいろな仕事できるようになることが楽しいです。また、出荷準備でパックをしているときに、特にやりがいを感じます。休憩時間中に仲間と話をすることも楽しいです。」
-苦労する点は?
「忙しいときや期限が迫っているときや、複数の業務を抱えているときは大変です。また、ラベルはがしなどの作業も大変です。」
-楽しかった出来事は?
「社員旅行でハワイへ行ったことです。ホテルの手配違いなどの経験も面白かったです。また、月に3回、バスケットボールクラブで汗を流しますが、会社のレクリエーションでもバスケットボールに参加していますので楽しいです。」
-今後の抱負は?
「ずっと仕事をして定年まで勤めたいと思います。今のように仕事と休みを充実させていきたいです」
- (イ)
- 上司の佐藤さんへのインタビュー
-Sさんの仕事ぶりは?
「現在の職務範囲にはないことも、自分からやり方を教えてほしいと申し出るなど意欲的です。以前、会社の制度としてSさんが長期休暇を取ったのですが、その時は職場が困るくらいで、改めてSさんが戦力になっていることを感じました。」
-Sさんはどんな存在ですか?
「とにかく話し好きです。Sさんがいると周りが明るくなります。休憩時間中なども、一人でいるところを見たことがありません。笑い話のようですが、話に夢中になりすぎて話し相手も一緒に送迎バスに乗り遅れたことが何回もあります。このため、乗り遅れそうなときは、『バスの時間だよ』と一声かけるようにしています。」
4.取組の効果
- (1)
- 障害のある社員の職務を創り出すことにより、職場全体の効率・生産性が向上した。
- (2)
- 障害のある社員がひたむきに仕事をする姿を目にすることで、障害のない社員にとって意欲を高める刺激となっている。
- (3)
- 日頃のコミュニケーションを通じ、職場全体が明るくなった。
5.今後の課題と対策・展望
- (1)
- 課題
短期的には特に課題はないが、長期的には、障害のある社員が高齢化したときの生活や通勤環境、仕事の多様性への対応などが心配な点といえる。 - (2)
- 対策・展望
今後もCSRの取組の一環として、法定雇用率の遵守並びに、障害のある社員及び障害のない社員も含めた生涯現役社会実現のための労務管理を模索したいと考えている。 - (3)
- 総括
最後に、今から障害者雇用に取り組む企業に対してアドバイスするとすれば、一番のポイントは、「思い切り」である。というのも、何事もやってみなければ分からないからである。また、その他を挙げるとすれば、次のとおりである。
- ア
- 雇う方も勉強である
障害者雇用を通じて、いろいろなノウハウを得ることができる。 - イ
- 雇ってから何をやってもらうか考える(最初から職務を限定しない)
雇用する前に職務を決めて雇用するのではなく、障害の特性や能力、制約に応じて柔軟に職務を決める。 - ウ
- 職務の創出は効果がある
職務の創り出しは、他の職務から切り出すことがベースになるので、全体として、無駄を省き、効率を上げ、生産性を高めることになる。 - エ
- 研修参加は効果がある
障害者雇用に係る研修会に積極的に参加することで、貴重な情報の入手、並びに労務管理の基本を学ぶことができる。 - オ
- ジョブコーチ支援を活用する
各種の支援機関や支援施設を積極的に活用することで、効果的な支援を受けることができる。
以上、一人目の障害者雇用の教訓を活かし各種の研修会に参加することで、障害者雇用に関するノウハウを学び職務の創出に成功したことが、結果として生産性の向上にも繋がるという、障害のある社員も障害のない社員も会社も三者三様に満足という好事例である。
執筆者:雨宮労務管理事務所 雨宮隆浩
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











