関係機関の協力により地元での雇用を進めた事例
- 事業所名
- 社会福祉法人洗心福祉会(法人番号 6190005000129)
- 所在地
- 三重県津市
- 事業内容
- 保育・介護・障害福祉・医療のサービス
- 従業員数
- 1,043名
- うち障害者数
- 14名
障害 人数 従事業務 視覚障害 5 針灸師、機能訓練員 聴覚・言語障害 1 介護補助作業員 肢体不自由 2 介護・保育補助作業員 内部障害 知的障害 4 介護・保育補助作業員 精神障害 1 清掃業務 発達障害 高次脳機能障害 難病 1 介護員 その他の障害 - ■本事例の対象となる障害
- 難病(潰瘍性大腸炎)
- 目次
-

事業所外観
1.事業所の概要
(1)事業・事業所の特徴
社会福祉法人洗心福祉会は、昭和53(1978)年に厚生省の法人認可を受け、翌年度に津市内に豊野保育所を開設し事業を開始した。その後、三重県内各地に保育所、特別養護老人ホーム、障害者福祉施設等を多数設立し、現在では、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、医療サービスを幅広く提供する県内随一の規模を誇る社会福祉法人になっている。
事業規模の拡大に伴って職員数も年々増加し、平成28(2016)年6月時点で1,043名(正規職員、準職員、パート)の職員が従事しており、約7割が女性である。
事業を行っている地域は、津市、松阪市、伊勢市、志摩市、伊賀市、鈴鹿市の6圏域にわたっており、職員数も千人を超える規模であることから、津市内に法人本部事務所を設置して経営・人事面を集約管理し、各事業所をサポートしている。各事業所における人事等での相談などについては、現地を訪問して対応することも多く、本部事務所の人材確保に努めている。
(2)経営方針
洗心福祉会は、以下の3つの理念をもとにサービスを提供している。
- 公器として地域社会に貢献する
- 事業を通じ安心と健康をモットーに、夢と希望を創造する
- 未来発展を目指し、人々の生活と社会の変化に常に誠意を持って前向きに取り組む
また、各事業所では、経営方針を毎朝職員が唱和して意識を高めている。上記の法人理念に基づき、少子高齢化が進む中で社会福祉事業の質・量を充実させながら、地域に根を張り地域福祉の拠点となるべく、日々の業務に臨んでいる。
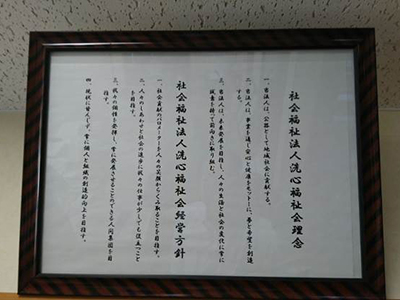
各事業所に掲げられている法人の理念
(3)障害者雇用の取組
洗心福祉会の障害者雇用率は平成28(2016)年4月時点で2.25%であり、全国及び三重県の障害者雇用率を上回っている。特別養護老人ホームにおける清掃業務や、多数の事業所を集約したベッドカバー等の洗浄業務など、大規模な社会福祉法人という特徴を生かした雇用を進めている。また、正規雇用が多く、雇用期間が長いことも特徴として挙げられる。除外率設定業種である保育所でも清掃員として障害者を雇用するなど、数字に現れない面でも積極的に障害者雇用を進めている。
さらに、障害者支援として、必要に応じて身元引受人と定期的な面談を行っているほか、障害者の生活支援を行っている団体と連携を図りながら、仕事に就けなくなった後も継続した支援を受けられるようにしている。
2.難病患者雇用の経緯、背景
(1)症状
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に腫瘍等ができる大腸の炎症性疾患であり、特徴的な症状としては下痢や腹痛がある。若年者から高齢者まで発症し、我が国の患者数は約16万人(平成25年度末の医療受給者証および登録者証交付件数の合計)、人口10万人当たり100人程度である(難病情報センターホームページより)。症状については改善、消失も認められるが再発する場合も多く、一般的には継続的な内科治療が必要とされる。今回の事例のAさんの場合、定期通院により症状は落ち着いている状況であった。
(2)雇用の経緯
Aさんを雇用する契機はハローワークを通しての応募であった。従来からAさん自身は介護の仕事をしたいとの希望を持っていたことから、前職についている間に介護資格を取得するなど、準備を進めていた。
介護人材の不足という状況もあり、Aさんの就職先の候補はいくつかあった。しかし、大規模な特別養護老人ホームであれば、職員1人当たりでケアを行う高齢者の人数も多く負担が大きくなる懸念があった。このため、本人の負担を考えると大規模な施設で夜勤の多い職場より、小規模な職場が望ましかった。偶然にも、Aさんの地元にちょうど洗心福祉会が運営する小規模な介護施設があり、通勤のしやすさもあって、そこでの勤務を当初から希望していた。
一方、同時期に洗心福祉会でも人材募集を行っていたが、Aさんの地元とは別の場所にある事業所での募集であった。このため、Aさんの希望を踏まえて、ハローワークと洗心福祉会が調整を行った結果、地元の事業所で雇用することが可能となり、Aさんの地元にある事業所で準職員として雇用することが決まった。
3.難病患者の従事業務、職場配置等
(1)職場の概要
勤務する事業所は、介護施設の類型としては小規模多機能型居宅介護施設に位置付けられる。小規模多機能型居宅介護施設とは、登録した高齢者が自宅から通って日中介護サービスを受ける「通いサービス」を中心に利用しながら、必要に応じて泊まりサービスや訪問サービスを組み合わせて受けることができる施設である。Aさんの働く施設は木材をふんだんに活用した温かみのある建物で、外見は一般の一軒家住宅と変わらない。屋内は事務室のほか、日中に高齢者が過ごす居間、浴室、宿泊用の部屋が数部屋という小規模な施設である。特別養護老人ホーム等と比べると規模も小さく利用者数も少ないため、利用者は落ち着いた環境でゆったり過ごすことができる。また、市街地から離れており、周囲は田んぼや山に囲まれ、自然環境にも恵まれた場所に立地している。

木材を活かした落ち着いた雰囲気の職場
(2)従事業務
Aさんの症状は比較的落ち着いており、従事業務は基本的に一般の職員と同じである。日中の食事、入浴などの介護サービス、泊まりサービスに対応した夜勤の業務も行っている。また施設では半調理(一定程度調理したものを温め盛り付ける等)も行っており、厨房に入ることもある。
施設が小規模であるということで、管理者の目配りも届きやすい。夜勤の業務もあるが、宿泊利用者は最大でも5名なので、特別養護老人ホーム等と比べて負担感は少ない。また、職員、施設利用者とも地元の人が多く、お互いに馴染みやすというメリットがある。このため、Aさんもまだ勤務して数か月であるが、全く問題なく勤務している。
(3)具体的な取組の内容
症状が落ち着いていることもあり、現在のところ施設として特別な支援は行っていない。Aさんは2か月に1回の頻度で通院しているが、受診予定日が勤務日に重ならないよう配慮している。その他適宜検査が必要になれば、同様に勤務調整をすることとしている。管理者としてはAさんの体調を気にかけているが、当然職員全体の体調ケアも同じように気にかけている。本人からも特に支障となる点や困っている点等もないとのことである。小規模な施設での勤務であるため、管理者が目配りしやすく、万が一問題が生じたとしてもすぐに把握、対応しやすい環境である。また、仮に体調が急変した場合でも、身元保証人を定めており、急なことがあれば連絡できるように調整をしている。なお、ハローワークから助成金の案内もあり、要件が整い次第、活用を検討する予定である。
4.今後の課題等
今回のケースは、勤務場所や勤務環境など、本人の希望どおりにマッチングできた理想的なケースである。当初は本人の希望する事業所と求人事業所が異なっていたが、関係者の調整により適切な雇用に結びつけることができた。
Aさんは症状も落ち着いており、一般の職員と変わらない業務を行っている。難病があっても症状の程度、進行等はそれぞれ異なることから、症状によっては全く問題なく勤務できることが分かる。難病というと症状が厳しいというイメージがあるかもしれないが、当然個人差があり、先入観を持たず個々のケースに応じて柔軟に対応していくことが求められる。
まだ雇用から数か月しか経過していないが、職場定着についてはこれから働いていく中で課題が出てくる可能性はある。今後、症状の変化が起こった場合に特別な対応が必要になるかもしれないが、小規模な職場で管理者の目も行き届きやすい職場であることが、この施設のメリットになると考えられる。
今後、需要が伸びると想定される高齢者福祉施設は、住民の身近な地域に設置されることが多いことから、その地域の障害や難病のある人の就労の場として大きな可能性を秘めている。住み慣れた場所での就労であれば、通勤もしやすく本人の安心感も増すだろう。さらに、高齢者福祉施設については、グループホームや小規模多機能型施設など、施設を小規模化する方向へ進んでいる。小規模化は主に利用する高齢者の環境を考慮している面があるが、同時に、施設で働く職員の業務環境にもメリットがあることをもっと強調してもよいのではないだろうか。
今後、高齢化が進み高齢者福祉に携わる人材が多く必要となっていく中、様々な障害や難病のある人が安心して住み慣れた地域で働くことができる職場が全国各地に増えていくことを期待したい。
執筆者:三重大学人文学部 法律経済学科准教授 石塚哲朗
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











