企画、広報、Webデザインなど、在宅勤務でクリエイティブな能力を発揮
- 事業所名
- 株式会社 笑顔デザイン研究所(法人番号 9130001054263)
- 所在地
- 京都市下京区
- 事業内容
- 写真ワークショップイベントの企画・運営(フォトレッスン、講演・研修会、写真展、トークライブなど)
- 従業員数
- 1名
- うち障害者数
- 1名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病 1 写真ワークショップ企画・運営 その他の障害 - ■本事例の対象となる障害
- 難病(肺動脈性肺高血圧症)
- 目次
-
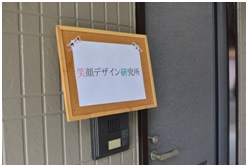
事業所外観

精華町のオフィス前で。所長とKさん(左)
1.事業所の概要
(1)事業内容
笑顔デザイン研究所は、“えがお先生”こと、笑顔写真家のかとうゆういち氏(以下、所長という。)を所長として、平成26(2014)年11月に設立。所長が「日本中に笑顔を咲かせたい」と活動してきた経験をもとに、写真・カメラを使った様々なコミュニケーションサービスを提供している。
写真ワークショップの企画・運営をはじめ、「親子フォトレッスン」など親子で一緒に楽しめるイベントの開催。「笑顔」をテーマにした、企業や自治体のポスター・CM・パンフレットなどの撮影・制作。その他、笑顔写真家が伝授する「笑顔を引き出す」の研修会、笑顔の大切さ・すばらしさを伝える講演会・トークショー、笑顔フォトの展示会、写真集の出版、コラムの連載など、「笑顔の写真」を軸にした様々な事業を展開している。
(2)企業理念
- ビジョン
子どもが”いい笑顔”で暮らせる文化を想像する。 - ミッション
あらゆる境界を越え、笑顔・感動・宝物を生み出そう。 - 行動指針
「主体性を信じます。その人自らが一歩を踏み出すキッカケを作ります。」
「ファシリテーターとなります。個々人が創造性を発揮できる環境づくりに勤しみます。」
「自らを以て体現します。第一に私たちが越境できることを示し続けていきます。」
2.障害者雇用の経緯・背景
(1)雇用までの流れ
所長は、大学4年の時に出会った子どもの笑顔に心動かされ、笑顔写真家として活動をスタート。平成21(2009)年より、全国各地の笑顔を写す「日本全国 笑顔の旅」に出る。翌年、出身地である新潟県で写真展を開催することになり、手伝ってくれるスタッフを探していた。その時に出会ったのが、九州の大学を休学し、新潟県内の企業にインターンシップに来ていたKさん。当時21歳だったKさんは、15歳で指定難病の「肺動脈性肺高血圧症」を発症し、以来、月1回の通院治療を続けていた。
写真展の感動を共有した所長とKさんは意気投合し、それをきっかけに親交を深めていった。以前から「子どもの話を聴ける仕事に就きたい」という思いを持っていたKさんには、所長の撮った子どもたちの笑顔写真や、人々との交流がとても魅力的に感じられた。また、所長は、物事を筋道立てて考えるKさんに自分にはない力を感じ、互いに認め合うようになった。約4年にわたる付き合いの中で、それぞれの個性や能力を引き出し合い、相互に補完し合う関係を築いた2人は「いつか一緒に働きたいね」とずっと話していたという。
個人で活動を続けてきた所長は、平成24(2012)年から妻の彩絵さん(当事業所の代表取締役/以下、代表という。)と二人三脚で活動するようになり、東北の被災地で子どもの笑顔を収めたチャリティ写真集の出版や、写真展・トークライブの開催、学校等での講演会など活動の場を広げていった。
一方、Kさんは2年間の休学期間中に3つのインターンシップを経て大学に戻り、卒業後は、「子どもと接する仕事に」と、山口県内で塾の講師として働き出した。それから2年ほど経ったある日、所長のもとにKさんから電話があった。「やっぱり所長と一緒に働きたい」と。Kさんのその言葉に、「時が来た」と感じた所長は、事業所を立ち上げる決意をし、代表とともに体制を整えた。
(2)障害者雇用の体制づくりとその背景
会社設立の決意を固め、まず取り組んだことは、会社としての方向性や将来ビジョンを明確にすること。3人が顔を合わせて、あるいは電話やスカイプ(インターネット電話)などの通信手段を使って、納得いくまで話し合い、1年がかりで経営計画や企業理念を構築した。そして、改めて「仕事」に対しての3人の考えが同じ方向を向いていることを確認し合ったという。
当時、所長夫妻はKさんから病気のことを聞いてはいたが、知っているのはほぼ病名だけ。「Kくんは病気のことをほとんど話さない。それが彼の気持ちの表れだと思っていたので、こちらも聞かないできた」と所長は話す。
Kさんは前の職場でも、学生時代にインターンシップを行った3つの企業でも、病気のことや必要な配慮について十分な説明をしてこなかった。「『月1回通院させてもらいます』とだけ伝えたが、働く前から『あれはできない』、『これはできない』と言いたくないという気持ちがあって、伝え方が甘くなってしまっていた。外見から病気が分かりにくく、傍目には普通の人に見られてしまう。それなら他の人と同じようにちゃんと仕事をしなければと思って自転車に乗って営業に回っていた。今から考えると少し無茶をしていたかも」とKさんは振り返る。福岡県出身の九州男児で、病気を発症するまでテニス部で毎日厳しい練習に励んできたという自負をもつ負けず嫌いのKさんには、仕事をするに当たって自分の病気が負い目に感じられたのだろう。難病があることを周囲に伝えずにきたため周りにサポートを求めるのも難しく、結果として無理な働き方をしてしまった。そこには、「病名を言っても十分理解が得られないかも」という思いもあった。
そんなKさんの思いに応えるために、所長と代表は病気について学習し、難病への理解を深めた。Kさんの病気「肺動脈性肺高血圧症」とは呼吸器系の疾患で、体を動かすとき、息苦しくなったり、疲れやすい、体がだるい、重篤なケースは意識がなくなる(失神する)などの症状がある。Kさんの場合、月1回の通院治療と服薬を続けていれば、日常生活を送ることに問題はない。Kさんと話し合って無理なく働ける仕事の内容や進め方、治療と両立しやすい就業規則を作成し、長いスパンで働ける体制を整えた。
会社設立の準備期間に50時間以上かけてじっくり話し合い、何度も確認し合ったことで、3人の信頼関係が深まった。Kさんの病気や治療のことも含めて、3人が何でもオープンに語り合えて、必要なときにすぐ相談・連絡ができるよう、常に連携を深めておくことも心掛けているという。
3 .障害者の従事業務
(1)具体的な作業の内容
一緒に会社を設立しようと思った理由は、それぞれの特性や能力に応じて役割分担を考えたとき、3人のバランスが非常に良いと直観したからだという。所長はプレイヤーとして現場に立ち、代表は営業・渉外担当、そして、Kさんはマネージメント業務を担当。会社を立ち上げる前から、3人の業務分担は組立てができあがっていた。
実際に、Kさんは「企画・広報」の肩書で、イベントやワークショップの企画、ホームページのデザイン、Webを通しての情報発信、経理などを担当し、クリエイティブな部門で能力を発揮している。「感性、感情で動く所長に対して、Kくんは理論立てて考えるタイプ。まさに補完関係なんですよね。例えば、所長の講演会でもプログラムの設計をしているのはKくんです。話す内容から構成、話し方までKくんがディレクションしています」と代表。
会社のホームページの制作もKさんが担当した。事業内容を「福祉」、「保育」、「教育」、「人権」、「経営者」の5つのカテゴリーに分類した見やすい構成で、カテゴリーごとに資料がダウンロードできるようになっている。
「彼が現場に出ることは多くないが、現場が円滑に進んでいくよう“手立て”と“仕組み”を考えて、現場の後方支援をしてくれている。これまで私がやってきた仕事は多岐にわたっているが、それをKくんがすっきりと整理して、とてもわかりやすいホームページを作ってくれた。これによって、これからの会社の進むべき方向が見えた気がする。Kくんは我が社の大切な戦力です」と、とても嬉しそうに話す所長からは、Kさんの仕事ぶりを高く評価していることを窺い知ることができた。

精華町オフィスでの打合せの様子
4.取組の内容
(1)勤務形態見直しの背景
会社を設立した当初は、京都市下京区にあるオフィスに3人が出勤する体制をとっていた。内勤中心のKさんに対し、所長と代表は外での活動がメインになるので、オフィスにはKさんが一人だけで作業する日が多かった。3人がそれぞれに「業務の効率化を図るために、もっと良い勤務形態があるのではないか」という思いを持ち始めていた。
そんなある日、京都府内に転居して新しい病院に通うようになったKさんは、治験新薬を勧められ服用し出したが、それが合わなかったのか、仕事中に体調が悪くなってしまった。少し動いただけでも呼吸が苦しくなり、急きょ病院へ行くことになった。
この出来事をきっかけに3人で話し合い、勤務形態を見直し、変更することを決めた。Kさんには体の負担が少なく、じっくり作業に集中できる在宅勤務を採用。週2回だけ会議や打合せのため所長夫妻の住居を兼ねる精華町オフィスに出社することにした。週に1度は3人で昼食を共にし、プライベートな話などもしながらコミュニケーションを図っているという。
(2)在宅勤務の導入
Kさんの業務内容は、企画や構成、広報、Webデザインなど、主にクリエイティブな部門を担当している。在宅勤務体制を取り入れることができたのは、その作業がパソコンに向かってする個人ワーク中心であったからだ。そして、通勤による負担がなく、自分のペースで仕事が進められ、柔軟に休憩がとりやすいこの勤務スタイルは、難病のあるKさんに適していると考えられる。
週2回出社日があるとはいえ、一人離れた場所で仕事をするので、これまで以上に、社内コミュニケーションを大切にしなければならない。そこで『トークノート』というアプリを活用し、双方向で意見交換ができる環境を整えた。「今から始めます」、「終わりました」といった始・終業時の報告をはじめ、当日の仕事の進捗と翌日の予定を伝える「業務報告」、また、Kさんの一日の体調を本人が5段階で報告する「体調チェック」も日々の日課になっている。
在宅勤務の就業時間は、7時45分~16時30分。火曜日・木曜日の週2回は精華町オフィスへの出社日である。京都市内に住むKさんが、精華町まで通うのに片道約1時間かかるので、通勤時間も身体に負荷がかかる。それを考慮して、出社日は終業を1時間前倒しにし、15時30分までとした。これによって電車の混む時間を避けて通勤できることになった。
(3)在宅勤務体制における配慮
Kさんの体調が悪くなった一件は、改めてKさんの病気と真剣に向き合うきっかけになった。体調の変化を感じ取れる兆候はあったのに、Kさん本人も経営者サイドもそれを的確に把握できていなかったことを反省し、「日常的に体調を把握しておく」ことの大切さを3人に強く感じさせた。現在では、突発的な体調不良に備えて、日々の体調変化を見逃さないよう以下のことを実践している。
(ア)毎日、Kさんから送られてくる体調の5段階判定が、「普通」を表す“3”を下回り、“2”や“1”が出てきた時には、どのように体調が悪いのかを必ずヒアリングする。
(イ)月1回の通院で薬が変わることがよくあり、これまでの経験から「薬が変わった後は体調の変化が起こりやすい」ということがわかったので、病院へ行った後は次の会議の際にその内容を報告する。Kさんは在宅勤務について、「毎日通勤しなくてよいというのは、身体的にも精神的に非常に楽です。ただ、あまり出かけなさ過ぎるのも良くないと思うので、週2回の出社というのは程よいペースだと感じている」と話す。代表は、「これまで以上に3人の連携をとって仕事の効率化を図り、現在週2回の出社を来年度には週1回にしていきたい」と考えているという。

在宅勤務でパソコンに向かうKさん
(4)支援スタッフの存在
Kさんは、昨年4月に福岡県から京都府内に転居し、それまで通っていた病院から京都市内の病院に変わった。新たな病院で治験新薬を勧められ、服用するようになったが、それが合わなかったのか、頻繁に体調不良を起こすようになった。それまでの環境から病院が変わり、医師が変わり、薬が変わり、病気との付き合い方が変わった。その不安を誰かに相談したいと思ったKさんは、ソーシャルネットワークサービス(以下、SNSという。)を活用して、ハローワーク西陣に難病患者の支援コーナーがあることを知り、自らその窓口を訪ねた。支援コーナーの担当ケースワーカーに新薬について相談し、主治医とも相談の上、服用を中止して体調は改善された。
これまでの主治医は、日常生活に負担のないよう症状を安定させて様子を見守っていく対処療法を主体とする医師であったが、Kさんが新たに選んだ医師は、病気への取組が先進的で、積極的に治験新薬を試し、先進医療に取り組んで行こうというタイプである。経験上、Kさん自身新しい薬を服用すると体調不良が起こることもわかってはいるが「これからも積極的に新薬を試していきたい」とKさんは考えている。
京都府内に転居して日が浅く、人間関係が多いとはいえないKさんにとって、ケースワーカーに話を聴いてもらえたことで、とても気持ちが楽になったという。「病気のことは誰にでも話せるわけではない。これまでの職場などでも難病を開示せず、1人で抱え込んできたので、“病気のことを話せる人がいる”というだけで本当にありがたいと感じている」。自分の病気に対する新たな理解者が増えたことを心から喜んでいるのが伝わってくる。現在も1~2か月に1度、体のこと、仕事のこと、メンタル面など様々な相談にのってもらっている。これから新たな治験にトライするときにも、この支援スタッフの助言を得て不安な気持ちを乗り越えて行くにちがいない。
5. 障害者雇用の効果、今後の展望と課題
(1)取組の効果
日本全国に笑顔を咲かせ、人と人を笑顔でつなぎたい。そんな想いを抱いて所長が一人で笑顔写真家の活動をスタートさせ、笑顔の旅、講演活動、写真展の開催を続けている所長に共感し、代表に手伝ってもらい平成23年(2011)に写真集を出版した。この頃から仕事の幅が広がり、活動を通して体得したコミュニケーション撮影術を使い、保育・子育て分野の仕事で活躍するようになった。
そして、Kさんが加わって、作成したホームページによって、最近は、自治会や企業のポスター・CMの撮影、法人向けの仕事の依頼も増えてきている。
「所長が一人ではじめたことですが、所長を通して、笑顔をどう波及させるのかは、もはや私もKくんも“自分ごと”になっている」と代表は言う。
Kさんは「自分の能力にあった業務だと思う。所長がこれまで行ってきた活動や仕事の延長線上に会社が存在しているので、私の役割はそのサポート役です。『子どもが“いい笑顔”で暮らせる文化・環境をつくる』という同じ目的をもって、所長が現場で仕事をしやすいようアシストすることにやりがいを感じている。体調のこともあるので、自分のペースで進められるのも、仕事を続けていける大きなポイントだと思う」と話してくれた。
また、経営者サイドの働き方にも影響があったようだ。「夫婦2人だけで仕事をしていたときは、ズルズルと夜遅くまで働くこともあったが、Kくんが加わり、Kくんが快適に働けるよう就業時間を短くしたら、私たちも短時間で効率よく、健康的に働けるようになった」。
「子どもの声を聴ける仕事に就きたい」と言っていたKさん。それは昨年度に実現した。所長がステージに立ち、Kさんが企画から司会進行まで担当したワークショップが、子どもの創造性と未来を拓くデザインを顕彰する『キッズデザイン賞』を受賞した。
Kさんはこれまで3つの企業でのインターンシップと、学習塾の講師を経て、ここが5社目。「インターンシップで学んだ仕事づくりやチームづくり、塾で身に着けたプログラム作成の力。それらがすべて今の仕事に生かされている」とKさんは言う。
難病のことを開示したことで、治療と両立させながら、働きやすい就業体制の中、仕事が続けられている。フォローしてくれる人々にも恵まれている。自分の体調に合わせて、「こう働きたい」という思いが実現されたことで、Kさんのワーキングライフにおける満足度はかなり高いように見受けられる。また、「京都に来て、“大切な人”と思える女性との出会いもあったんですよ」とプライベートの充実ぶりも代表が教えてくれた。
(2)今後の展望と課題
仕事先や周囲の人に病気を開示できず、苦しんだ時期もあったが、現在27歳になったKさんは、SNSで自分の病気について公表し、情報発信を行っている。同じ病気の人と情報交換したり、病気で悩む人からメッセージが届いたりと、良い交流が生まれているようだ。「難病というくくりの中でも、いろんな病気の人がいる。例えば、同じ病気の人や似たような症状の人が、毎日どんな生活をし、どのような働き方をしているのか、というのは参考になるし、励みにもなる」というKさん。
高校1年、15歳の春に突然「難病」と診断されたKさんは、「僕、このまま死ぬのかな」と思ったという。それから12年。毎日の体調チェックの5段階評価は、“3”が6割、稀に“4”が付くことはあっても、「快調」を表す“5”が付くことはない。「日常的に“快調”ということは、これからもないのかもしれない。でも、いかにこの体調と上手く付き合っていくかなんだと思う」という。そんなKさんが病気と向き合い、受け入れ、これからも付き合っていく姿を、所長と代表は今後も見守って行こうと考えている。「Kくんの病気へのスタンスを尊重しながら、私たちができる限りの体制を整え、働きやすい環境を整えていきたい。仲間として長くやっていきたいので」と思いを語ってくれた。
執筆者:藤原 幸子(フリーライター)
- ビジョン
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











