難病(パーキンソン病)患者への取組事例
- 事業所名
- 社会福祉法人 ふるさと自然村(特別養護老人ホーム「陽だまりの里」)(法人番号 6490005004669)
- 所在地
- 高知県南国市
- 事業内容
- 介護福祉事業、老人ホーム運営
- 従業員数
- 735名
- うち障害者数
- 21名
2016年6月1日現在
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 11 生活相談員、介護員 内部障害 知的障害 5 介護員 精神障害 2 介護員 発達障害 2 介護員 高次脳機能障害 難病 1 看護師 その他の障害 - ■本事例の対象となる障害
- 難病(パーキンソン病)
- 目次
-

事業所外観
1.事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
社会福祉法人ふるさと自然村は、平成8(1996)年3月に設立され、その後、介護老人福祉施設や通所及び訪問介護事業所、有料老人ホーム、特別養護老人ホームなどを開設・運営し、現在、高知県内に多数の特別養護老人ホームなどを開設している。
「笑顔と安心のある施設づくり」、「第2の我が家」をモットーに、利用者の安定した生活の確保のために、自立と生きがいの持てる施設作りを目指し、職員一人一人が障害に対する深い知識や専門性・人間性を持てるよう、組織として人材育成にも努めている。
同時に、「地域住民の憩いの場」、「地域の防災拠点」としての役割も目指している。
そのうちの特別養護老人ホーム「陽だまりの里」が、今回の難病患者が勤務する施設である。
(2)障害者雇用の経緯について
- ア.特別養護老人ホーム「陽だまりの里」の状況について
-
特別養護老人ホーム「陽だまりの里」においては、平成28(2016)年3月末で、正看護師が1人辞めることになり、後任の正看護師の採用を検討していた。
特別養護老人ホームは、利用者(入所者)の人数により配置しなければならない看護師の人数が決まっていて、「陽だまりの里」では、利用者が50名いることから、看護師が最低2名必要であった。
また、特別養護老人ホームは、原則、65歳以上で介護認定が要介護レベル3以上の利用希望者が対象となるが、「陽だまりの里」では、利用者の平均年齢が90歳代となっており、利用者50名のうち半分以上が、一番レベルの高い要介護レベル5に認定されていることから、通常の特別養護老人ホームよりも、全体的に介護が必要な度合いが高いところである。
このように「陽だまりの里」では、利用者の高齢化や重度化に加え、「看取り介護」という、終末期を迎えた利用者が安らかに過ごせるようケアをするという、人間の最期に立ち会う重大な業務もあること、そして「くらしのサポート」、「生活をする場を支える」が理念であることからも、業務の質を保ち、更に向上させるために、最低限の看護師2名にとどまらず、より多くの看護師の配置が必要となっていたところである。
- イ.難病患者Aさんについて
-
Aさんは、パーキンソン病と診断され、今も手足の震えや動きが緩慢になる症状に悩まされている。それでも、ハローワークの難病患者就労サポーターと何度か面接を行いながら、再就職を考えていたところ、社会福祉法人ふるさと自然村、そして「陽だまりの里」を紹介された。
「陽だまりの里」は、社会福祉法人ふるさと自然村の一施設であるため、採用面接は法人本部である、社会福祉法人ふるさと自然村が一括で実施し、その後、「陽だまりの里」を含めた、特養老人ホームなどに配属されることとなっている。
Aさんは、正看護師の資格を所有しており、「陽だまりの里」の求める条件とは一致しているものの、体調面に不安はあった。そこで、自身のことを包み隠さず、「(難病の症状により)できないこともある」ことを、最初から正直に面接時に話した。それでも働く意欲は持ち続けていたことから、その点を評価され、平成28(2016)年4月1日付けで、正職員として採用に至った。
結果的に、「陽だまりの里」にとっては、タイミングよくAさんを採用することができた。
現在、正職員の正看護師1名、準看護師2名、非常勤の正看護師1名、準看護師1名の体制となっている。
- ウ.その他の障害者雇用について
-
Aさんの他に、現在「陽だまりの里」と同じ建物に併設している「ケアハウスつくしんぼ」には、発達障害のある職員2人(男女1人ずつ)がおり、障害者職業センターのジョブコーチが支援を行っている。
女性職員のBさんは、トライアル雇用の後、「ケアハウスつくしんぼ」に正式に雇用され、現在に至っている。男性職員のCさんは、トライアル雇用中である。
ジョブコーチがCさんの様子を見に来るついでに、Bさんの様子も確認しているが、特段、問題は発生していない状況である。
Aさん、Bさん、Cさんに対して、後述する瀧施設長が自ら声を掛け、話を聞くようにしている。いろいろため込まないよう、声を掛けることにより、負担を軽減できるよう努め、人間関係が円滑に進むよう気を配っている。
2.取組の内容と効果
(1)Aさんの仕事内容について
Aさんは高知市内に住んでおり、「陽だまりの里」のある南国市への通勤は、バスで30分ほどかかり、その後、最寄りの停留所から歩いて10分ほどかかる。
当初は、運動になると思っていたものの、夏場の暑い日には多少きつい日もあったが、続けて出勤している。
就業時間は、8時30分から17時15分までで、昼休みが1時間あり、夜勤はない。概ね週4日ほど働いている。
普段の仕事内容は、まず朝、出勤して、情報収集のために夜勤明けの職員から申し送りを受け、前日までの利用者などの状況把握をした後、バイタルチェック(血圧、体温測定、呼吸確認など)を行う。特に、入浴前にはバイタルチェックは必須となる。また傷のある利用者には処置、バルーンカテーテルなどのチェック、薬のチェック、食事介助、排泄介助などを行う。
直接的な医療行為は行わないものの、多くの利用者が高齢で、かつ50名全員に対して、これらのことを実施するとなると、当然のことながら、午前中で全て終わることはなく、午後まで断続的に続き、体力的にも相当大変である。

Aさんのデスク
(2)Aさんの職場内における状況について
Aさんは、自身の症状について、職場のみんなにオープンにしている。こうすることにより、状況を共有することで、職員同士がサポートしやすくなり、Aさんへの周囲の理解も進むことになった。
業務中、どうしても症状から来る手足の震えなどにより、他の職員のサポートが必要になるときがある。
例えば、利用者に対して、点滴をしたまま動けるようにするための持続点滴を行う際に、注射針を刺す手の震えが気になり、他の職員に代わってもらうなど、業務内容によってはサポートが必要なときがある。また、動作が緩慢になり、細かい作業ができなくなることもあるので、そのようなときは、早めに薬を飲むなど、対処はしている。
薬の服用は、基本的には朝、昼、晩で、仕事中に飲む場合、12時と15時に飲むことになる。薬を服用する時間帯についても、職場内でオープンになっている。薬の効果が切れ始める、12時前や15時前は、多少調子が悪くなることもあるが、周囲の職員は了解済みである。言い換えれば、周囲の理解を得られてしまうくらい、Aさんの働きぶりは、普段から周囲を納得させる水準のものである。年齢の近いDさんのサポートもあり、人間関係は極めて良好である。
また、体調が悪いときには、勤務時間などを変更するようにしていて、それが認められているが、職場内への悪影響は特に発生していないところである。

ミーティングスペース
(3)施設長の理解
「陽だまりの里」の施設長、瀧さんは職場内における環境作りを重視している。
どこの組織にでもあるように、「陽だまりの里」においても、担当する業務や立場の違いによる相互理解が進まないこともあったが、瀧施設長が関係部署の意見に耳を傾け、一つ一つ調整に努めた結果、互いの立場の相違を理解しようとする姿勢が職員間に生まれ、良好な職場環境に変わっていった。
Aさんのパーキンソン病についても、一つの個性として周囲に認識してもらい、全てオープンにすることで、病気の特性を共有し、結果、サポートを得やすい環境につながっていった。
また、外部(施設利用者及びその親族なども含む)の利用者に不要な不快感を与えないよう、「まずはあいさつをする」、「何事も率先してやる」など、見落としがちな基本的かつ重要な姿勢を改めて徹底したことが、結果として、回りまわって、職場環境の向上につながっていった。瀧施設長という管理職のトップが全体に気を配り、調整し、理解することが、Aさんの働きやすさにもつながっている。
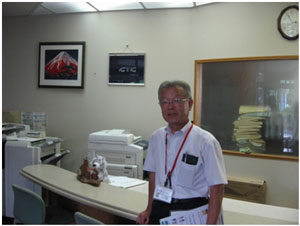
「陽だまりの里」瀧施設長
3.今後の展望と課題
Aさんは採用当初、環境の変化に伴い、直近では半日勤務しかできなかったこともあり、フルタイムで働くことに、体がついていかないことを感じていた。
しかし月1回、主治医の診察を受けるなど、体調管理に気を付けることで、現在のところ症状は安定しており、フルタイムで働くことにも体が慣れてきたように思われる。
採用してから3か月くらい経ち、瀧施設長に「今後もよろしくお願いしたい」との希望を告げ、Aさんは決意を新たにしたところである。
瀧施設長は、日ごとに変化する病状の詳細までは分からないので、とにかく無理はしないでほしいと思っている。
Aさんは、今年度採用にも拘わらず、喀痰吸引に係る指導者研修も受講した。できることなら何でもやりたいという意欲があり、体調に気を付けながら、幅広い業務を担当したいと思っている。また、瀧施設長も、Aさんの高い能力を評価し、他の職員を指導できる立場になってもらいたいと願っている。
執筆者:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部
高齢・障害者業務課 伊藤 辰雄
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











