「個性を活かす」職場
~ 向合う、頑張る、やり抜く。 ~
- 事業所名
- 一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院(法人番号 2380005002480)
- 所在地
- 福島県郡山市
- 事業内容
- 脳疾患の基礎的・臨床研究と予防、診断・治療及び、総合診療科、救急医療、福祉分野など(除外率設定業種)
- 従業員数
- (法人全体2,352)名
- うち障害者数
- 22名
障害 人数 従事業務 視覚障害 1 事務 聴覚・言語障害 2 事務、看護 肢体不自由 9 事務 内部障害 5 リハビリテーション、検査、看護 知的障害 1 介護、事務等の補助業務 精神障害 3 介護、事務等の補助業務 発達障害 1 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害
- 精神障害、発達障害
- 目次
-

事業所外観
1.事業所の沿革と事業内容
一般財団法人脳神経疾患研究所 (附属病院等を含む理事長は渡邉一夫氏、(以下「南東北」と記す。)は、福島県・宮城県・青森県の3県に基盤を置き、病院・診療所・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・身体障害者療護施設などを運営、医療・福祉のグループ事業体である。株式会社日本格付研究所では、南東北の格付けをA-(安定的)としている。
南東北は、昭和56(1981)年の南東北脳神経外科病院の開設から35年を経て、現在は、1 都4 県で8 病院を運営する「南東北グループ」(総長は渡邉一夫氏)の中核法人である。附属する総合南東北病院、南東北福島病院の他、南東北医療クリニックなど10診療所、5介護老人保健施設及び6居宅介護支援事業所、5訪問看護ステーションや8通所リハビリテーションセンターなどを統括運営し、東北3県の医療・介護業務の一翼を担う。平成28(2016)年12月1日現在、南東北の従業員数2,352名(うち障害者22名)が就労する。
沿革は、以下のとおりである。
沿革(概要) 昭和59(1984)年 財団法人脳神経疾患研究所設立 平成2(1990)年 名称変更:財団法人脳神経疾患研究所 附属南東北病院 平成8(1996)年 附属老人保健施設ゴールドメディア開設
附属南東北病院訪問看護ステーション開設
附属南東北病院在宅介護支援センター開設平成9(1997)年 附属南東北訪問看護ステーションたんぽぽ開設
附属福島医療クリニック開設
医療法人実践会 南東北福島病院開設平成10(1998)年 名称変更:財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 平成11(1999)年 社会福祉法人南東北福祉事業団 総合南東北福祉センター開設 平成18(2006)年 総合南東北病院が地域医療支援病院の名称を許可(医療法第4条) 平成20(2008)年 総合南東北病院が厚生労働省「地域がん診療連携拠点病院」の指定
附属南東北がん陽子線治療センター開設平成24(2012)年 名称変更:一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 最近の表彰は、同グループ医療法人の平成25(2013)年「イクメン企業アワード」初代グランプリ受賞(厚生労働省)、平成25(2013)年救急功労者表彰(総務大臣表彰)などだが、ISOの認証取得(品質・環境)でも、社会的装置としての責任を示している。先進医療の積極性は、民間病院では世界発とされる「ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)」の取組みは特徴的である。推進する附属南東北BNCT研究センターでは、福島県の助成を受けて平成28(2016)年に治験を開始したが、東日本大震災からの復興に寄与する期待も大きい。
2.障害者雇用の概況
(1)障害者雇用の経緯と経営トップの姿勢
病院と言う事業体は、医師や看護師など高度な専門性を有する技術者集団であるとも言えよう。一般市民からすれば目線の高さを感じるかも知れない。理事長の渡邉一夫氏は、南東北グループ説明の中で次のように経営理念を述べている。「私たち『南東北病院グループ』は福島県、宮城県、青森県の東北3県を基盤として、病院・診療所・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・身体障害者療護施設などの施設を展開する医療・福祉の総合企業体です。グループ創設以来、私たちは最先端の機器や技術の導入と知識の習得に努めてきました。しかし同時に、最高医療・福祉サービスの本質が、相手を慈しみ、思いやる心、つまり「人間愛」にあることを忘れたことはありません。それは、私たちの理念“PRO VONO AEQUNOROSA(すべては、患者さんのために)”として凝縮されているのです。」である。
経営的な言葉で言えば、「CS」(患者の満足度)となるのだが、開院以来の着実な規模拡大には、地域に支えられて来たこと、地域における存在価値の評価、であろう。大事なことは、「人間愛を忘れぬ」ということではないか。ここで気付くのは、「人間愛」とは被用者に対しても同義であることだ。言わずもがな、事業体の最大資産は、「人」である。院是は、また、「ES」(従業員の働きがい等)=「人質(じんしつ)」に裏打ちされた「CS」=「品質」と言うこと。つまり、医療従事者・患者・経営の「三方よし」と言うことになろう。
南東北の35年の院史をふり返り、障害者雇用にも歴史の積み重ねがあった。と話すのは、附属総合南東北病院総務課、課長心得の甲賀明美氏である。その言葉に、障害者雇用を単に美風としない真剣さを垣間見る。松下幸之助の言葉に「理を優先し、情を添える」とあるが、「理」とは物事のメカニズムであり、「情」は情緒であろうか。院是の意図するところは、地域におけるCSR(社会貢献)の総体であろう。
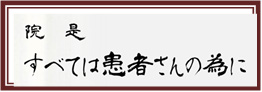
(2)障害者雇用の現状
甲賀氏は真摯な人である。平成25(2013)年に今の職場に異動されて、現職は障害者雇用を開発する立場にもある。言わばミッションの動機付けとなったのは、「障害者雇用納付金制度」であったと言う。いわゆる、「納付金」対策のためだとするが、実際は、ハローワーク主催の企業合同説明会などで、多くの障害者(児)の面接に時間を割いていたのである。その中で、「もう少し、考慮すれば…。」との思いに至ったと話される。このようにして、実雇用率は、企業グループ算定特例や除外率制度を含む法令遵守に結び付いたのである。
南東北において、各年度末の障害者雇用の推移(重度障害者のダブルカウント含む)は、平成22(2010)年が19名、平成25(2013)年21名、平成26(2014)年26名、平成27(2015)年29名、平成28(2016)年には30名になったが、当初は、身体障害・看護の臨時雇用でスタートしたと言う。障害者雇用の経年実績と、特に、配属職場で障害の理解及び障害特性に向合うことで、平成26(2014)年度からは、従来の障害概念や職場環境の見直しも図りながら、被用者の障害種別について広く捉えることで、事務職での正規採用などの路を拓いていった。平成27(2015)年より精神・発達障害者、平成28(2016)年にも発達障害者の採用に至っている。
平成28(2016)年12月1日時点での南東北の障害者雇用数は、22名(男性12名、女性10名)である。障害の種類別では、身体障害が17名(視覚障害1名、聴覚・言語障害2名、肢体不自由9名、内部障害5名のうち重度は9名)、知的障害1名、精神障害3名、発達障害は1名である。また、年齢構成は19歳から60歳代に及ぶが、平均年齢は40.9歳である。勤続年数は、入社1年の新人を含む平均就労は9.9年である。現在、南東北での基本的な雇用形態は、正規雇用と臨時雇用であるが、正規雇用者が多数を占めている。
3.取組の内容
(1)雇用管理と適正化
南東北の障害者雇用のルートは、主にハローワークを介した通年募集と、特別支援学校などである。障害者枠での職域は、開発・進展の方向とみられる。今後の障害者雇用促進法の改正(法定雇用率引き上げ等)を見据えれば、既に「売り手市場」の現状理解と、精神障害者(含む、発達障害者)の雇用促進であろう。
採用後のフォローアップにおいて、配置職場での各人の適性や観察などから、マッチングと作業の習熟を図っている。被用者と雇用者の双方に、「試用があってこそ適応もできる」所以である。就労形態は、障害者枠の人も一般社員と同様の7.5時間/日労の勤務体系で、全員が被用者保険の対象者である。
業務の切り出しについて、甲賀氏は、「障害のある人で、看護師が一日中歩き回っている状況を見て、自分も何かをと思って動いてしまう。それで、疲れ切ってしまう。」などや、臨機応変性が求められる業務ラインでは、「『適職』の見出し難い状況もあった。」と言う。大事なことは、「人財」(人質〔じんしつ〕)の視点ではないか。その思いは、紋切り型の「合理的配慮」ではなく、一人ひとりの「強み」を引き出し、如何に伸ばして行けるか、仕事に対するモチベーションの強化と言うことになろう。
(2)職務能力の把握と雇用の安定化
現在、南東北の障害者枠での担当業務は、専ら、軽作業やルーチン化された定型業務等であるという。事務室作業の他に、中材(中央材料室)や通所リハ(リハビリテーション)での補助等である。職場の定着率も定年退職等を除けば良好だと言う。好定着率は雇用管理によるが、具体的には、ア 臨時雇用の採用者も、正規雇用へ登用の路が開かれていること、イ 訪問型ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援、ウ 本人の日常生活面を支援する地域の就労支援機関との連携、エ 業務上の資格取得の援助などである。本人が業務遂行する支援や、当該職場に対しては、職務や職場環境への調整等、助言などもある。
甲賀氏は、「特に、精神や発達の方の定着率が高い。」と話す。職場ベースで、配置者の障害特性等について、ボトムアップ的な学習機会を設けたと言う。それでも、「走りながらだ。」とされ、職場適応についても職場のチームワークが重要だと示された。
通所リハ、中材、事務室に勤務する3名(発達、身体)にインタビューした。
Aさんは、通所リハで介護補助を担当する。「利用者さんと話をするのが楽しい。」としながらも、対人関係の苦手さは「自分マニュアルやルール化」等でと工夫をみせる。更に、介護技術や作業療法など治療的な資格を取得して、「自分をステップアップしたい。一般枠での就労も目指してみたい。」と笑顔で話す。
Bさんは、中材に勤務してチームリーダーも担っている。業務は、主にオペ室や病棟等で使用した器材の洗浄・消毒・滅菌等である。「病院の総てに係る仕事なので、いい緊張感を持ってやっている。」と言い、日々、やりがいを感じていると話す。その上で、「職場スタッフと、仕事や交流のバランスを取りながら…」、既に業務上の資格も取得しているが、「より専門性やスキルアップを目指してやって行きたい。」と話す。
Cさんは、総務に所属する。主に、電話の受付や郵便発送・宅配便の受取り等を担務する。その上で、「職員の業務がスムーズに行くよう、代替など出来る範囲での対応を心掛けている。」と、職場のサポーターなのだ。そして、「家族や職場のサポートを受ける身からの自立を目指している。」とも話してくれた。
筆者が思うには、それぞれ異口同音に語る「縁の下の力持ち」、「黒衣」の利他性である。当に、「人間愛」が感じられて、凛とした活き方が素晴らしい。
4.取組の効果と期待
第一番には、「誰もが、仕事があること、『出来る』実感があること。」。そして継続性だと甲賀氏は話す。概観すれば、一つは、職場のチームワークと働く環境への配慮であろう。二つには、障害を「体質」と捉えて、「向合う、頑張る、やり抜く力」を賦活させて、やりがいや充実感、責任感へ向かう各人のパーソナリティを育んで来たと言えよう。
折しも、厚生労働省は、医療従事者の勤務環境の改善(改正医療法)を軸に、「勤務環境改善マネジメントシステム」を勧告する。医療機関での、「医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、‥‥快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること」を目的とする。甲賀氏は言う。単調で繰返しの作業などは、ヒューマンエラーを起し易く、緊張で疲労感も厳しい。加えて危機管理も考慮される。例えば、発達障害の人は、「仕事の熱心さや丁寧で正確さもある。」。そうした、行動特性的な分担を受け容れて行くことで、障害者雇用の信頼財も深まり、職場運営もスムーズになった。
平成28(2016)年12月、厚生労働省発表の「平成28年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業の雇用障害者数(47万4千人余)、実雇用率(1.92%)ともに過去最高を更新したと言う。また、ハローワークを通じた当該就職件数は、90,191件(平成27〔2015〕年度)で対前年度比6.6%増である。このポイントは、特に精神障害者は38,396件(増率11.2%)や発達障害者等が3,894件(含む、高次脳機能・難治性疾患;増率21.1%)の就職件数の大幅増である。産業別にみても、医療、福祉(33,805件)への就職件数が最も多い。
南東北の意識は高く、特に、精神障害者や発達障害者等の雇用機会も期待される。
執筆者:臨床発達心理士・社会福祉士 星郁夫
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











