障害者が業務に専念し、能力を発揮できる環境を整備
- 事業所名
- 深川医療器株式会社 福山営業所(法人番号 1240001017514)
- 所在地
- 広島県福山市
- 事業内容
- 福祉用具レンタル・販売、車いすオーダーメイド・販売、医療用品卸売業、住宅改善改修(バリアフリー対応)
- 従業員数
- 41名(全社91名)
- うち障害者数
- 3名(全社5名)
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 3 営業、事務 内部障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害
- 肢体不自由
- 目次
-

福山営業所 外観
1.事業所の概要と障害者雇用の経緯
(1)会社の沿革と概要
昭和32(1957)年に呉市で深川機械店を創業。医療機器を販売する傍ら、労働災害による身体障害者への車いすの制作を開始。昭和54(1979)年に株式会社に組織変更し、深川医療器株式会社を設立。医療機器主体の販売業務から車いすを中心とするリハビリ機器販売に転換を図る。福山営業所の沿革は下記の通り。
平成3 (1991)年 福山営業所を開設 平成10(1998)年 現住所(福山市)へ移転。 平成13(2001)年 身体障害者を採用 平成16(2004)年 福山営業所を新築 平成25(2013)年 福山営業所を増改築 現在は本社を広島市に移転し、福山営業所、呉営業所の3拠点で、車いすのオーダーメイド、医療・福祉用具の販売、介護保険による福祉用具のレンタル、住宅改修等を行っている。
(2)障害者雇用の経緯
同社は車いすをはじめとする身体が不自由な人が利用する医療・福祉用具の販売やレンタル業務を行なっており、車いすを実際に使用する立場で顧客に対応できる人材の必要性を感じていた。
障害者雇用への思いはあったが、実績や準備はなく雇用には慎重であった。しかし、平成10(1998)年の福山営業所の移転に伴い人事を刷新したタイミングで、営業担当者として障害者を新規に採用。車いす利用者の立場で寸法や使い勝手などをアドバイスでき、顧客のニーズに添う製品やきめ細かいサービスを提供できる人材として育成してきた。
現在、障害のある社員は福山営業所に3名、呉営業所に1名、広島本社に1名が勤務しており、全拠点で活躍している。
2.取組の内容
(1)職場環境の整備
平成13(2001)年に障害者を雇用した時点で、福山営業所内にはまだ車いす対応のトイレは完備しておらず、所内は段差がある上に手狭で、障害のない社員も立ったまま作業をしている状況だった。車いすの営業ではメンテナンスや修理も行うが、必要な作業スペースを所内に確保することができず、屋外で作業をしていた。
障害のある社員が業務を行う上で無理や我慢を強いる環境を改善し、仕事に専念できる環境を整えるため助成金を申請。最初に取り組んだのが、車いす対応トイレの設置と障害者の雇用を増やすことを前提とした肢体不自由のある社員が運転できる営業車の導入であった。
平成16(2004)年に営業所を新築する際は、障害のある社員の意見を取り入れ、社員だけでなく会社を訪れる障害のある人が出入りする際、負担にならない設計とした。1階~3階の各フロアはバリアフリーで、エレベーターを設置。トイレは各階とも、電動車いすの重度障害者も安心して利用できる広さを確保している。
特に1階は、営業所を訪れる車いす利用者も抵抗なく出入りできる環境にするため、障害のある社員の意見を隅々に反映。車いすのメンテナンスや改造を行う作業スペースも車いすで出入りしやすい十分な広さで、自由に動けるレイアウトにしている。車いすに乗った状態で全身が確認できる大きな鏡のほか、カフェのようなしゃれたディスプレイで、気軽に話ができる明るい雰囲気になっている。

肢体不自由のある社員が運転できる営業車

1階トイレ

1階作業スペース
2階は事務所と応接室、3階は障害のある人のための訪問看護ステーション「リバティ」とベッドなどのある多目的ルームに加え、ミシンを置いた加工場が設けられている。
1階の作業スペースでオーダーメイドの車いすの採寸、調整、修理とともに、車いすのパーツやクッションの加工作業を行うほか、3階の加工場では縫製がすぐにできるため、メーカーに近い、迅速できめ細かい対応が同営業所の強みとなっている。

3階 ミシンのある加工場
(2)営業所内の風土づくり
入社から20年にわたり、福山営業所の責任者として障害者雇用と人材育成に携わってきた取締役の小川廣三営業本部長は、障害をハンディキャップではなく個性と捉え、障害の有無に関係なく給与面も業務でも社員を対等に処遇する姿勢を一貫してきた。
障害のある社員が働きやすい職場環境とは、設備面の整備だけでなく、社員間で共に働く意識付けができているかも要素の一つである。
障害のある社員だからと腫れものに触るように気を遣い、特別扱いするのではなく、できることとできないことを明らかにし、障害のある社員自身にできることは任せ、できないことは障害のない社員がフォローするというフラットな関わりを大切にしてきた。
障害のある社員と障害のない社員が互いに遠慮したり、依存したりして無理をする関係は、双方が負担を抱えることになり、長くは続かないからだ。
また、障害の有無にかかわらず、社員一人ひとり気持ちの持ち方や考え方は様々だ。障害のある社員の場合においても、障害の度合いも障害に対するとらえ方もそれぞれに異なる。障害者雇用において十把一絡げの一律の対応は通用しない。先に雇用した障害のある社員を基準(モデル)にして、後に雇用した障害のある社員にも同じものを求めたり、接したりするのではなく、個々に合った接し方を考慮し、他の社員への周知を図りながら対応している。
3.障害のある社員の声
吉浦繁幸さん(入社16年;肢体不自由)
福山営業所を増改築する際、設計段階からかかわらせてもらい、車いすで存分に仕事ができる環境ができました。うれしく思うとともに、自分もそれにかなう業績を上げていかなければと、仕事に対する意欲がそれまで以上に高まりました。入社当初から、本部長は私の性格や考え方を尊重し、本音で相談や話し合いができました。障害者である以前に、営業担当者として社内でも社外でも通用する仕事の心構えや取り組み方を教えられ、私自身も意識し、実践してきました。私も管理職となった今、自分の経験を踏まえ、障害のある社員が遠慮なく相談できる存在でありたいと思っています。
営業の仕事も人間関係を作るところから始まります。車いすを必要とするお客様が何を求めているか、私自身も車いすを使っているからこそ心を開いて話をしていただくことができ、私もお客様の要望を自分のこととして受け止めることができます。
私がお客様と会社をつなぐ窓口となり、車いすをきっかけに当社と生涯にわたるお付き合いをしていただけるような関係を築いていくことを心がけています。お客様に信頼していただける仕事をすることが喜びであり、やりがいにつながっています。

入社16年、
現在、係長の役職に就く吉浦さん4.管理者の声
小川廣三 営業本部長
当社に障害者雇用の実績や経験がなかったからこそ、雇用した障害のある社員へは責任がありますし、雇用した以上、企業の一員として業績を上げる人材に育てなければ、と思いました。
障害のある社員が身体面でも気持ちの面でも働きやすい職場にするために、本人と対話を続けてきましたし、障害のない社員に対しても障害のある社員に対する目配り、気配りが自然にできるよう意識づけをしてきました。
「できないだろう」「できそうにないから」と障害のある社員を手助けすることは簡単です。手を貸せば、業務も早く済むかもしれませんが、不親切なようでも障害のある社員本人が挑戦し、自分でしようとしていることをあえて手助けしない勇気もまた必要です。見て見ぬふりや無関心でいるということではなく、相手を気にかけ、気を利かせるという配慮は、どんな職場でも求められ資質と思うからです。
営業担当の障害のある社員にまつわるエピソードがあります。営業車で在宅の顧客先に商品を届けに行く際、地図で見る限りは何の問題もなく見え、本人も営業車で届けに行くつもりでいましたが、実際は急な斜面にある家で、障害のある社員が営業車を止め、車いすで商品を運ぶのは困難な場所でした。地理的状況を知らないまま顧客先へ向かった障害のある社員が、商品を届けることができずに営業所に戻ってくる可能性があることに気づき、その顧客先へは他の社員を向かわせました。
このように障害のない社員にとっては何でもないことが、障害のある社員には「できない」という挫折感を味わうことになりかねません。こうしたケースをなくすための「気配り」「目配り」を営業所内で徹底するよう心がけてきました。「できないのは障害があるからだ」と不要な挫折感を抱いてほしくないし、同じ職場にいる者たちが抱かせてはいけないと思ったからです。
できないことがあれば他の社員に頼む、無理や我慢をしていると気付けば、障害のある社員に声をかけて手伝う。こうした障害のある社員が本当に必要とするサポートを自然にできる関係は、私だけでなく、営業所内の全員で試行錯誤しながら積み重ねてきたものです。
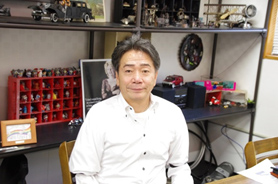
小川廣三 営業本部長
5.今後の課題と展望
福山営業所では、これまで営業と事務で身体障害のある社員を雇用してきたことから、知的障害者、精神障害者の雇用に向けての受け入れを試みたこともあるが、知的障害者、精神障害者に対応する体制が十分でなく、育成以前に営業所内のバランスが崩れる事態を招いた。営業・事務業務ともに顧客や病院等の医療関係者と接することが多く、良好な人間関係を築く必要性があり、現在も知的障害者、精神障害者を雇用するには至っていない。
しかし、同営業所では障害のある社員を含む社員の定着率が高い。小川本部長は雇用に際し、障害の有無や履歴、試験結果にこだわることなく、顧客の視点で「この人からものが買いたい」と思えるか、を雇用のポイントにあげる。人物重視の基準で雇用された社員は、営業所内では一人も退職することなく、やりがいを感じ各ポジションで業務に従事している。
今後も障害の有無にかかわらず意欲のある人材を育てる構えだが、60年にわたり医療・福祉に携わってきた経験とノウハウ、ネットワークを生かし、新たな個人顧客向けのサービスと社内の仕組みづくりを行い、将来的には知的障害者、精神障害者を含む障害者雇用の枠を広げていきたいという考えで、すでに準備が始まっている。
執筆者:神垣あゆみ企画室 神垣 あゆみ
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











