障害者に合わせた職場環境事例
- 事業所名
- 株式会社いちやまマート玉穂店(法人番号 9090001000172)
- 所在地
- 山梨県中央市
- 事業内容
- スーパーマーケット
- 従業員数
- 138人(正社員 24人、パート・アルバイト社員等 114人)
- うち障害者数
- 4人
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 1 レジ部門 内部障害 知的障害 1 青果部門 精神障害 1 ミート部門 発達障害 高次脳機能障害 難病 1 ミート部門 その他の障害 - 本事例の対象となる障害
- 知的障害
- 目次
-

事業所外観
1.事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
株式会社いちやまマートは、昭和33(1958)年4月創業、昭和39(1964)年7月法人設立し、現在の代表取締役社長は三科雅嗣氏で、山梨県内11店舗と隣県長野県に2店舗の合計13店舗を展開する、従業員数1,100人のスーパーマーケットである。経営理念・信条は、「健康的な食生活が幸せをもたらす~毎日の食事が私たちの身体を作っています。だからこそ美味しくて、安心、安全な食品を提供することに努めています~」である。
本部機能を併設するイッツモア玉穂店(以下「玉穂店」という。)は、営業時間、来客数も他店とは異なる大型店舗で、中央市に平成5(1993)年10月に開店した。店長は甘利元氏(以下「甘利店長」という。)である。
(2)障害者雇用の経緯
玉穂店は「人にやさしい店づくり」をコンセプトに、障害者等専用駐車場の設置、車いす専用買い物カートや目の不自由な人への買い物サポート、多目的機能トイレの設置をはじめ、盲導犬、介護犬、聴導犬を同伴することもできるなど、障害者に配慮した店舗づくりを心がけている。今年度の店舗の運営方針は、障害者・高齢者へ配慮した店づくりであり、商品やレイアウト、見やすいPOP、設備など、さまざまな側面から障害者・高齢者に対する買い物へ寄り添い、やさしくサポートするしくみになっている。
障害者雇用についても甘利店長を中心に積極的に取り組んでおり、現在4人の障害のある社員が働いている。甘利店長は、昭和56(1981)年に入社、青果部門・店長代理・青果トレーナー・貢川店店長・塩部店店長を経て、平成21(2009)年玉穂店店長に就任、現在に至っている。甘利店長が生まれ育った地元の源地区には、知的障害のある児童・生徒を対象とした特別支援学校の山梨県立わかば支援学校(以下「わかば支援学校」という。)がある。生徒数は230人、小学部・中学部及び高等部の3学部で構成されており、「たくましい力ゆたかな心」を教育目標に、卒業後、社会の一員としてそれぞれの場で安定した社会生活を営むことができる児童・生徒の育成、支援が行われている。
甘利店長は、自治会活動を通じわかば支援学校と地元の源小学校との交流や共同学習推進会議の副委員長として活動した経験がある。そのほかにも、地元の源地区自治会連合会長、わかば支援学校の評議委員、源小学校PTA会長、わかば支援学校交流推進委員を務めており、そうしたことが契機となり、わかば支援学校生徒の卒業後の夢(就職)の実現に向け、玉穂店での雇用が進められることになった。
次に玉穂店では知的障害のある方として初めて採用したわかば支援学校卒業生のAさんについてレポートする。
2.取組の内容と効果
(1)取組の内容
- ア.
- Aさんの障害特性を知ること
Aさんの「障害特性」、「過去の経験や技術」、「できること」、「得意としていること」などをインターンシップや面談、仮採用の期間をとおして知ることから始めた。これらの期間があったことで、Aさんも職場もお互いを知ることができ、マッチングの精度を高めることができた。指示に対する理解力がどれ程あり、作業のスピードは速いか、周囲との協調はどうかなど、作業を行うことではじめて見えてくることが多いからである。そして、Aさんは、純粋で話をしっかりと受け止めることができるとともに、常に明るい笑顔ができることが分かり、双方の歩み寄りはスムーズであった。
- イ.
- Aさんが働き続けられるための支援をできる限り行うこと
関係者が連携して支援を行うことが大切であると考え、Aさんの保護者、甘利店長と担当課長(リーダー)、山梨障害者職業センター(以下「職業センター」という。)の4者が連携していくこととなった。具体的には、初めての知的障害のある方の雇用ということもあり、職業センターのジョブコーチ支援を利用することとし、4者でジョブコーチ支援計画などについて検討した。また、ジョブコーチ支援などの進捗状況を確認するための定期的なミーティングも実施し、保護者をはじめとする関係者の情報共有を図るなどAさんの就労をサポートする体制を整えた。
- ウ.
- Aさんの業務、任せる仕事を設計しマッチングを図ること
知的障害者の場合、一般的に定型作業や同一作業の繰り返しに長けているという特長から、Aさんには、それに合わせた仕事の切り出しを検討し、青果部門での軽作業を担当することにした。青果部門での就業を検討した理由は、他部門に比べるとスライサーの使用などの危険を伴う作業が少なく、複雑な作業手順を覚える必要がないこと、また臨機応変な対応を求められることが少ないなどの理由からである。野菜を切る際に刃物の使用はあるが、家庭用の包丁レベルであり、必ずペア作業で行うことを徹底しているため、ケガのリスクに対する配慮が行われていると考えたからである。
また、Aさんは、複雑な作業手順を理解したり、記憶したり、1回聞いただけで間違わずに遂行することが苦手であるため、まずは、無理のない仕事を担当するとともに、作業手順が身に付くまで丁寧に指導することが重要であった。作業への適応状況を時間をかけて把握し、Aさんに合った仕事の割り振りやAさん本人に合わせた仕事を切り出すことで、Aさんの強みが生かせるようになった。仕事に合せるのではなく、Aさんに合わせて仕事のマッチングを図った。
- エ.
- 教育担当者とのペアによる反復演習
Aさんに対する指導・育成は、教育担当者(教育係)の社員を決め、教育係とのペアで同じ作業を始めることから始めた。教育係は、障害のある社員(Aさん)に作業内容などの説明・指導を行ったうえで、自分も一緒になってペアで作業をする。例えば、大根カット袋詰め、値段付けを行う作業の場合、包丁・まな板・手袋・袋・原料について、必要な量を全てセッティングしてから、切り方を教え、一緒に作業する。このとき、「昨日できているから、今日もできると思うのではなく、今日は今日で説明をすること。昨日と同じようにしてほしいという指示の出し方では伝わらない」と考え、誤解や食い違いが生じないよう、焦らず、ゆっくり、理解の程度を確認しながら具体的に解説していくことを心がけた。Aさんの間違いは伝える側の責任ととらえ、対策を講ずることとした。そして、こうした取組には時間と労力を要することから、ペアが担当する業務の作業量は、通常の社員1人分の作業量と同じで構わないとの設定でスタートした。
Aさんは、当初の切るだけの作業から、袋詰め、値段付けまでの作業ができるまでに成長し、更に3か月程で簡単な指示であれば単独での作業が可能となり、今では売場への陳列、補充ができるまでに成長した。
- オ.
- 現場の受け入れ理解
Aさんとの仕事上のコミュニケーションはどうするのか、適切な話題は何か、障害のない社員も気を遣うため、受入れ部署以外の社員に対しても、受入れの際に知っておいてもらいたい事項を研修などを通じて理解を深めるなど、受入れ体制を整えておく必要があった。Aさんの受入れを決定する前に、Aさんと同じ勤務時間の社員に対して、障害者雇用の現状や生活上の課題などについて社員自身の家族に置き換えて話すなど理解を深めるための工夫を行った。このようにAさんの受入れ体制を整えたことにより、実際にAさんの勤務が始まると、当初の懸念は払拭され、お互いの違いを認め多様性を理解することで、社内に認識が共有され人間関係も円滑になるという効果があった。同じ作業を行う社員は、自分にAさんと同じ年頃の家族を持つ世代だったこともあり、温かく受け入れられた。
Aさんの受入れを工夫し、配慮のある職場環境を整えても、誰もが、新しい環境の中に入るときには不安があり、一歩踏み出すには勇気がいる。最終的には、同僚の心からの笑顔が、Aさんの不安を払拭させたのである。
- カ.
- 職場までの通勤支援
Aさんは、当初、平成28(2016)年4月からの入社予定であったが、家から勤務先である玉穂店まで約9kmということであったため、通勤手段を原動機付自転車とし、免許取得後の5月に入社することになった。しかし、原動機付自転車では危険だとの家族からの申し出により、普通自動車免許を取得後の入社に再度変更になった。その後、普通自動車免許を取得し、毎日家族が同乗しながら、通勤時間帯に練習を行うことで、一人での通勤が可能となったことから同年9月からの入社となった。4月の入社予定からは、半年近くも経過していた。勤務日は、月曜日から水曜日と金曜日、日曜日の週5日間、勤務時間は、9時から16時(休憩70分)とした。甘利店長は、「家族の継続した努力(根気)と職場の同僚の理解と協力が必要なことを改めて勉強させてもらった。実際、入社予定日が、何度も変更になったが、障害者雇用とは個々の実情に配慮し、Aさんのように段階を踏むことの必要性を理解することではないか」と話す。
Aさんが自家用車で通勤するために家族の協力で練習期間を設け、職場の同僚の理解と安心を得て入社したように、自立して働き続けるためには、個々の実情に応じて段階を踏むことも必要ではないかと筆者は考えた。

野菜の梱包作業の様子
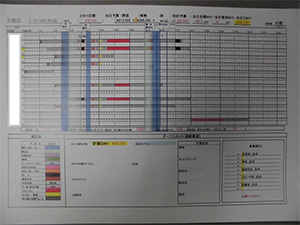
青果部門作業表
(Aさんの作業も含まれる)
焼き芋の品出し作業の様子

品出し(完了)
(2)取組の効果
企業である以上、生産性を問われるが、障害者の賃金面、作業効率、障害者雇用納付金制度や助成金など、メリットもあることを伝え、他の社員の理解を得ている。障害者雇用を考えた場合、対象者の障害特性などを理解した上で、本人に合う仕事を設定することで十分に戦力になるものと考えられる。また、障害者の受け入れをスムーズに行うための方策を職場内で話し合う中で、障害の有無にかかわらず結果的に職場全体が働きやすい環境が生まれるというメリットがある。具体的には、作業内容を見直すことによる職場全体の安全管理や生産性・効率性の向上、職場の雰囲気や同僚に与える影響である。障害のある社員と一緒に働くことで、周りの社員が人間的に成長することや、リーダーシップを発揮し社会的視野を広げさせることができる。そして、障害者の雇用は、働きやすい職場づくりにも貢献しており、ひいては、店舗のコンセプトでもある「人にやさしい店づくり」にもつながっていると甘利店長は考えている。
3.今後の展望と課題
特に知的障害のある社員については、まず得手不得手をしっかり理解した上で、仕事に習熟してもらうための仕組みを整えることが必要である。特に、個々の障害特性等を把握し、活躍できる仕事を設定すること、能力を向上させるための指導方法と環境を整備すること、受け入れる現場の同僚に対し理解を求めることが重要である。
しかし、このように、受け入れに関する最低限の知識や職務設計、職場環境整備さえ行っていれば、誰を採用しても活躍が期待できるわけではない。知的障害者とひとくくりにしても、個々人によって異なり、性格も違えば、得意な業務、働く意欲にも差がある。このことは、障害の有無にかかわらず同じことが言える。このため、自社の業種や社風に合う人物かどうかを見極めることが重要であることから、採用時のサポートや採用後のフォローを行っている職業センターなどの支援機関を活用することが有効であると考えている。また、数多くの障害者を雇用することがゴールではなく、個々の障害のある社員が「ここで働くことができて良かった」と思いつつ、定年退職を迎えるまで長く働き続けられるような仕組みと職場環境を整えることが重要であると考えている。
障害のある社員に限らず、生活の費用を稼ぐという目的だけで働いている訳ではなく、働くことで人から感謝されることの喜びを感じ、それが毎日を生きる原動力になると考える。甘利店長は、職場が障害のある社員にとってそのような存在になることを考えている。
最後に、甘利店長は、人生の大半を過ごす職場において、大切にしている思いがある。それは「恕(じょ)」の精神である。「他を受け入れ、認め、許し、その気持ちを思いやること」を大切に、障害のある人にもない人にも、一人ひとりにこの精神で接することこそが、全ての成功の秘訣になっていると語った。
執筆者:はやかわFP社会保険労務士事務所
主宰 早川 朋子
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











